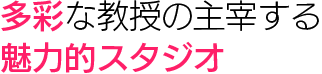小西 泰孝 |
 鈴木 明 |
 高橋 晶子 |
 布施 茂 |
 菊地 宏 |
 持田 正憲 |
 長谷川 浩己 |
 小松 宏誠 |
 永山 祐子 |
 大島 芳彦 |
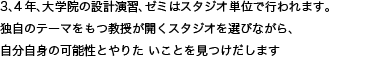
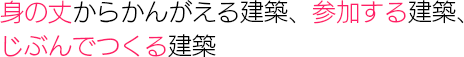
鈴木スタジオでは、身の丈(みのたけ)にはじまるふるまいと、
周囲に構成される空間とモノの配列(しつらい)と架構から、
建築を考えることに重きを置きます。
そのために街を歩きまわり小さな気づきを繰り返し、
ディテールを発見し、それを鉛筆を用いて原寸で描くことを通じ、
建築を身体で感じ考えることを大切にしています。
さらに、都市の使いかたと参加のしかたを考え、実践することで、
さまざまな公共空間や公共施設のありかたを提案していきます。
スタジオでは以下のことを進めていきます。
1. セルフビルドによって実際に建築をつくること、
2. 小さな建築だけでなく都市の公共空間や公共施設の計画に参加すること
3. 身体にもとづく自由なプロダクトや空間をデザインし、研究すること
4. ワークショップを通じて利用者と建築計画を練り、新しい使い方を見いだすこと
5. ル・コルビュジエをはじめとする近代建築、現代建築の研究をすること

ベニヤの家

Tea42

ポリテクチャー

国立西洋美術館
における
ワークショップ

設計計画Ⅳ
身の丈の家
鈴木 明(Suzuki Akira)
教授(博士・工学)
1953年東京生まれ
武蔵野美術大学卒業
武蔵野美術大学大学院修了(造形学修士)
東京理科大学論文博士(2021)
連絡先:akirasuzukimusabi.ac.jp
専門分野:建築計画、建築論、インタラクションデザイン
研究テーマ:建築と身体(モデュロール身体の図像学)、セルフビルド建築
主な作品:
〈セルフビルド建築〉
新聞紙の家(新聞紙ドーム)、ベニヤの家(ベニヤドーム)、積み木の家、水道管の家、ポリテクチャー、モバイルハット(Tea42)、モバイルハット(Bar42)
〈インタラクションデザイン〉
せんだいメディアテーク(伊東豊雄設計)のサイン計画、多摩美術大学図書館の家具コンセプトほか
〈ワークショップ〉
「建築教室」(キュレーション:降旗千賀子)目黒区美術館、1997年より開催、「NAiオランダ建築家協会におけるベニヤの家」2000、「森の建築教室」国際芸術センター青森、2002、「第3回ベルリンビエンナーレにおける新聞紙ドーム」2004、
〈個展、共同展(招聘)〉
「鈴木明x山田正好展 東のすみか西のひと ライフ・リ・サイクル」(キュレーション:岡部あおみ)、art space kimura ASK?、2005、「Shelter and Suvival」広島現代美術館、2008、
〈展覧会キュレーション〉
「4+1/2: The Internal Landscapes of Tokyo」Today’s Japan展の建築部門展、ハーバーフロントセンター、トロント、カナダ
主な著作
『Do Android Crows Fly Over the Skies of an Electronic Tokyo?』Architectural Association School of Architecture, London, 2000
『インタラクションデザイン・ノート』神戸芸術工科大学大学院、2003
『建築教室の教科書—子どもとあそぶ家づくり』建築都市ワークショップ、2007
『つくる図書館をつくる―伊東豊雄と多摩美術大学の実験』(共著)鹿島出版会、2007
主な論文
〈発表〉
「ル・コルビュジエのモデュロールに描かれた身体の図像に関する研究」建築学会、2010~2013
担当科目:
建築計画C
設計計画II
設計計画III
設計計画IV
卒業制作
大学院